2025年夏、日本中を驚かせたニュースがありました。
それは、静岡県伊東市の田久保真紀市長による「学歴詐称」疑惑。
「東洋大学法学部卒業」と公表していたものの、実際は大学を除籍処分となっていたことが明らかになり、世間の大きな非難を浴びました。
市議会からは辞職勧告が出され、7月7日に市長を辞職しました。
今回の騒動をきっかけに、改めて注目を集める「学歴詐称」。
学歴を偽ると、どんな問題になるのか?罰せられるのか?
この記事では、事例と法律の両面からわかりやすく解説していきます!
▶️学歴詐称とは?どこからがアウト?
「学歴詐称」とは、自分の最終学歴や在籍情報などについて、意図的に事実と異なることを記載する行為を指します。
たとえば…
- 大学中退なのに「卒業」と記載
- 短大卒なのに「大卒」として応募
- そもそも通っていない大学名を経歴に加える
これらは、履歴書や面接、プロフィールなどにおいて「事実に反する情報を提示する」という点で、詐称(虚偽記載)に該当します。
学歴は、採用や報酬、昇進などの判断材料にもなるため、正確であることが前提。
それを意図的にごまかせば、契約関係そのものに大きな影響を及ぼします。

▶️一般企業での学歴詐称:バレたらどうなる?
◯ 懲戒処分・解雇の可能性
民間企業で学歴詐称が発覚した場合、最も多い対応が懲戒処分や解雇です。
特に、「大卒以上」など明確な要件があった場合、それを満たしていないとわかれば、採用そのものが無効と判断されることもあります。
また、「昇給・昇進」が学歴をもとに判断されていた場合には、詐称が損害賠償の対象となる可能性も。
◯ 実際にある企業の対応例
- 即日解雇:大卒と偽って入社→中退が判明→採用取消
- 役職剥奪:管理職に昇格後、学歴詐称発覚→降格と減給
- 退職勧告:円満退職を促す形で処理されることも多い
「採用段階での虚偽申告は、企業との信頼関係を損なう重大な問題」として、多くの企業が厳しい姿勢を取っています。
▶️公務員・政治家はどうなる?より重い責任
民間よりもさらに厳しく見られるのが、公務員や政治家などの公的ポジションです。
◯ 選挙で学歴を偽った場合
地方自治体の首長や議員などが、選挙活動中や公報・選挙公約などで虚偽の学歴を記載した場合、これは「公職選挙法第235条」に違反する可能性があります。
【公職選挙法 第235条(虚偽事項の公表)】
当選を得る目的で、虚偽の経歴・学歴等を公表した者は、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処される。
つまり、「卒業していないのに卒業と偽る」ことは、法律違反となる可能性があるのです。
さらに悪質とみなされれば、当選無効・公民権停止処分もあり得ます。
▶️最新事例|伊東市長・田久保真紀氏の学歴詐称
◯ どんな問題だった?
田久保真紀氏は、伊東市長選の選挙公報や市広報誌で、自身を「東洋大学法学部卒」と記載していました。
しかし2025年6月、「実際は除籍処分で卒業していない」という事実が報道によって明らかに。
本人は会見で、「卒業したと信じ込んでいた」と説明しましたが、多くの市民や市議会はこの説明に納得しませんでした。
◯ その後の展開
- 市議会は百条委員会(強い調査権限を持つ)を設置し、真相解明に動き出す
- 辞職勧告決議が市議会で可決される
- 2025年7月7日、ついに辞職を表明(ただし、出直し市長選に立候補する意向も)
学歴詐称による「辞職勧告」や「百条委員会」の設置は極めて異例であり、政治的な信頼失墜の深刻さを物語っています。
▶️法的リスク:詐欺罪・私文書偽造にも?
学歴詐称が悪質な場合、刑事罰の対象となることもあります。
たとえば…
- 卒業証書を偽造して提出→「私文書偽造罪」(刑法159条)
- 学歴を詐称し、採用時に不正な利益を得た→「詐欺罪」(刑法246条)
これは「うっかりミス」では済まされず、懲役刑を含む重大な犯罪になる可能性もあります。
▶️嘘がバレる時代に、学歴詐称は通用しない
一昔前なら、「履歴書に書いただけ」「卒業証明なんて見られない」…と高を括っていた人もいたかもしれません。
しかし、いまや学歴はデジタルで照会可能な時代です。
- 大学の卒業証明はオンラインで即確認できる
- 過去の発言やSNS記録もすぐ掘り返される
- 匿名の告発がSNSで拡散される時代
現代において、学歴詐称はすぐにバレるリスクのある行為なのです。
▶️学歴詐称、なぜここまで重く見られるのか?
学歴詐称は単に「ちょっと話を盛った」レベルでは済まされません。
その理由は次の3点です。
- 信頼を裏切る行為
採用や投票の判断に大きく影響を与える情報を偽る=信頼関係の根幹を破壊する行為。 - 競争の公平性を壊す
正直に努力してきた人の立場を不当に奪う行為でもあります。 - 公的な立場では“説明責任”が不可避
政治家や公務員は市民から選ばれ、税金で働いている存在。その説明が曖昧であってはならないのです。
▶️まとめ
いかがでしたでしょうか!?
この記事では、学歴詐称がバレた場合はどのように罰せられるのか?また法的にも罰せられるのか?ということについて徹底解説しました!
今回の伊東市長のケースを見てもわかるように、学歴詐称はたった一行の“嘘”で、
- 職を失い
- 信頼を失い
- 社会的評価を失う
非常にリスクの高い行為です。
特に公職にある人物や、影響力のある立場にある人ほど、
「正確な経歴」「透明な説明」「誠実な対応」が強く求められます。
就職活動・転職活動・履歴書・SNSプロフィール…。
あなたの学歴や経歴、誇張していませんか?
もしほんの少しでも「書きすぎたかも」と思うことがあれば、今すぐ修正する勇気が必要です。
学歴は、ただの肩書きではありません。
それをどう使うか、どう説明するかで、人の信頼は大きく変わるのです。
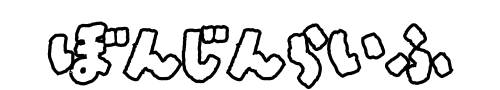


コメント